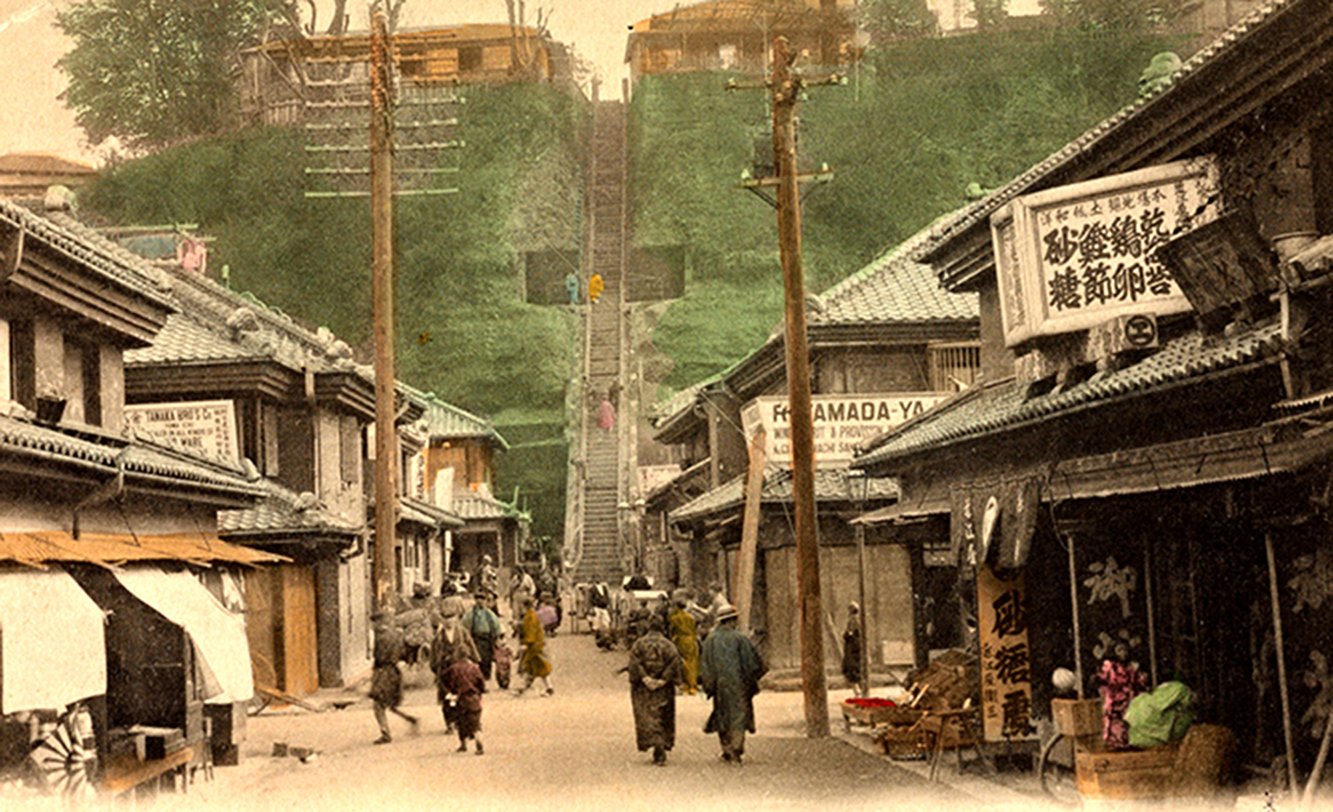ローマのバチカン市国は、カトリック世界の首都です。バチカン市国の象徴はサンピエトロ寺院(教会)ですが、現在の建物は17世紀に完成した2代目で、バロック様式で飾られています。一方、地質的に見ると、サンピエトロのバシリカを含む教会の建物群は、丘陵を構成する基盤岩類と沖積層の境目に建設されています。現在、バシリカ(大聖堂)へは階段を上って入るようになっていますが、この階段はスペイン階段と同様、基盤岩(鮮新世の砂岩泥岩)と沖積層の地層境界に相当します。手前の広場の部分には、軟弱な沖積層が分布するため、広場の裏手では地盤沈下の証拠も見られるほどです。
初代サンピエトロの受難
さて、初代のサンピエトロ寺院は、320年にコンスタンティヌス帝によって建てられたローマ風のバシリカでした。しかし、このバシリカは、1349年の地震によって深刻な損傷を受けました。この地震による揺れは、わが国の気象庁震度に直すと震度5強から6弱で、イタリアでも2~300年に一度は起きている規模の地震でした。しかし、この時の揺れで大被害となった理由は、ちょうど建物が堅固な基盤岩と軟弱な沖積層を跨いで建設されていたためです。つまり、両者の揺れの差によって被害が拡大されたわけです。コロッセオの被害と同じメカニズムですね。
サンピエトロ寺院の再建
その後、サンピエトロの再建は法王庁の悲願となりました。その結果、ジュリオ2世(在位:1503-1513)とブラマンテ、レオ10世(在位:1513-1521)とラファエロ、パウルス3世(在位:1534-1549)とミケランジェロのコンビによって、聖堂の基本型が作られたのです。その後、ウルバヌス8世(在位:1623-1644)の時代にベルニーニによって聖堂前の空間が広場として計画され、現在に至っています。ベルニーにプランは、広場の部分の地盤が軟弱で大規模な建物に適さない事を考慮し、逆転の発想で劇的な効果を作り出した、すばらしい設計です。
宗教改革をもたらした地盤
しかし、こうした教会の建て替えは、莫大な資金を必要としました。そのために、レオ10世は、贖宥状(免罪符)販売を企画し、購入者に全贖宥が与えられることを布告しました。しかし、この事に神学上の疑問を呈し、議論を挑んだのが、かのマルティン・ルターです。1517年11月1日に事件は起きました。この出来事は、キリスト教世界での宗教改革の発端として良く知られています。つまり、世界史は地盤条件によって作られた、と言えなくもないと思います。